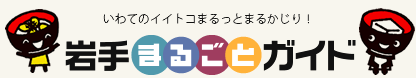三代にわたり、昭和の味を守り続ける
盛岡の中心部に位置する東大通商店街、通称「桜山」に、この街の歴史をみつめ続けてきた店がある。「そば処 吉田屋」が開店したのは1945年。もともとは松尾鉱山で食堂を営んでいたが、終戦に合わせて桜山へと移った。
現在店を切り盛りするのは、三代目の山崎浩二さんと、母の洋子さん。店名の「吉田」は、初代である祖母の名字だ。また、「そば処」と冠しているだけにはじまりが蕎麦屋だと思ってしまうが、中華そばのほうが歴史は古い。
味のルーツは、かつて材木町にあった食堂・喫茶の「晩翠(ばんすい)」。東京で腕を磨いた店主のもとで、祖母が修業。中華そばのつくり方もそのとき学んだ。煮干、鶏ガラ、豚骨を、にごらせないようにコトコトじっくりと煮込む。スープを口に含むと、素材の味わいがふんわりと広がる。ほのかな生姜の風味も感じられ、全体を引き締めている。
最初の頃は麺も手づくりだった。「戦後すぐの頃は、配給でもらった小麦粉を麺にして売っていたこともありました」
と、桜山歴70年の洋子さんは懐かしむ。
浩二さんは、母が調理する姿を見ながら育った。国鉄職員などを経て、30歳のときに家業に入る。小さい頃から手伝っていたこともあり、抵抗はなかったという。当時は父がリサイクル関連の仕事を営んでおり、浩二さんは両方を掛け持ちしていた。朝8時から空き瓶を引き取りに酒屋などを回り、11時には吉田屋に戻って店の手伝い。お客さんのピークが過ぎた13時半くらいからまたリサイクルへ。夕方に吉田屋に戻り20時ころまで手伝う。そんな日々が10年近く続いた。
「その頃は一日中ほとんど座ることがありませんでした。でも不思議とつらかったという記憶がないんですよね」
と笑う。
桜山育ちの浩二さんは周囲とのつながりも深く、家族のように付き合っている人たちも少なくない。昨年の4月、桜山で大きな火事があった。火元の傍に80歳を超えた一人暮らしのおばあさんが住んでいた。そのおばあさんとは惣菜のおすそ分けをする付き合い。出火がわかるやいなや、近くの「ラーメン厨房 シルクロード」の店主とおばあさんのもとへと向かった。煙が充満する中、間一髪だった。昔ながらの近所づきあいが、人命を救ったのだ。
「同じ場所で長く続けるということは、“人となり”がわかってもらえるということ。その信頼は味だけではなく、生活の面でも同じなんです」
浩二さんと洋子さんには、貫いてきたことがある。それは、調理法を変えないこと。毎朝6時からスープを仕込み、開店の11時に完成する。素材の比率も変えない。祖母の味、昭和の味がここにはある。
「流行の味を追いかけることも一つの方法だと思いますが、流行には廃りがある。それでは長く続けられません。流行は巡るものですから、以前は古かった味が新しいととらえられることもあります。継続は力なり、ですよ」
浩二さんは続けてこう言った。
「街づくりだって同じではないでしょうか。流行りに合わせて郊外にショッピングモールをつくっても、他の都市と変わりません。それよりも、古くからの街の個性を大切にしていくことのほうが差別化につながりますし、注目されると思います」
街づくりにも共通する普遍の定理が、丼の中に見えた。
(店情報)
住 盛岡市内丸4-10
℡ 019-622-9598
営 11:00~19:00
休 日曜祝日
P 無
(メニュー)
中華そば(並) 500円
カレー中華 750円他